
榎本隆之 先生
新潟大学大学院医歯学総合研究科 産科婦人科学 教授
分野 産婦人科
榎本先生の大きな手から紡ぎ出されるのは、癒やしの音色。溢れ出す患者さんの気持ちに応えたいという熱意。美しい音楽が優しく流れ、軽快な関西弁が縦横無尽に駆け巡る。絶えず音に包まれた楽しいDr.インタビューになりました。榎本先生の魅力をご紹介します!
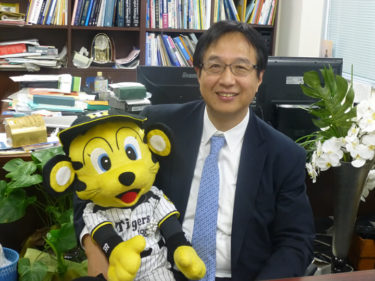
患者さんに寄り添うということ
榎本先生はロビーコンサートをやっていらっしゃるとか。ピアノを弾かれるんですね。
榎本:まぁ趣味程度ですけどね。小学校の時は嫌だったんですよ、ピアノ。レッスンの直前まで遊んでて、手が泥だらけ。親に連れられてピアノ教室行けば「手、洗いなさい!」から始まるやろ。それで弾かされる曲は練習曲ばっかりで、全然楽しくなく4年生の時習うのやめたんです。しかし、高校生の時運命の出会いがありました。ヴィルヘルム・ケンプというピアニストの生演奏を友達に連れられて聴きにいったんですよ。そのときベートーヴェンの『月光』を聴いて、これを弾きたい!と思ったんです。それで『月光』の楽譜買ってきて、まぁ第一楽章は弾けると思いまたピアノの練習を我流で始めたんです。週に一回ぐらい触る程度だったんですけど、ちゃんと習うべき時に習ってないので、テクニックもないし、指もまわらない。だから人前で弾くなんて考えてもみなかったんです。でもね、大阪大学病院に勤務してたときに、18歳の子宮頸がんの女の子が入院してて、まだ若いのに手術出来ないくらいの進行がんでした。でも高3の受験の時期で、音大に進む希望があったので、抗がん剤の点滴をうけながらも、キーボードを食台の上に乗っけて、ヘッドフォンで自分の音聴きながらよく練習してました。しかし、ある日、キーボードがなくて寂しそうにしてるから、「どないしたん?」って聞いたら、「ママが毎回入院の度にキーボード持ってくるのしんどいって持ってきてくれへんかった」だって。それで病院の外来受付の隅に誰も弾いてないグランドピアノがあったので、ピアノの鍵を借りて、入院患者さんの夕食の時間が終わってから、彼女とピアノを弾きに行ったんですよ。他の入院中の患者も「ピアノ聴きたい」といって4~5人付いてきました。彼女が弾いたあと、患者さんから先生も弾いて欲しいとお願いされたので、「しゃーないな。一曲だけやで」といってショパンのノクターンを弾きました。そしたら、たまたま一緒についてきた患者さんで、抗がん剤の副作用の嘔気で毎回苦しんでた人が、後で僕に手紙をくれたんですよね。そしてびっくりしたことが書いてあったんです。
「先生のピアノ聴いたら吐き気がとれました。点滴は今日で終わりやけど、先生がピアノ聴かせてくれるならもう一回、二回抗がん剤の点滴を受けてもいいと思いました。」
ええっ??て思うでしょ?音大ピアノ科を卒業した人でも、全員がコンサート活動をしているわけじゃない。まして僕のようなアマチュアが人前で弾くなんてそれまで考えたこともなかったんですけども、患者さんの前で下手なピアノを初めて披露したら、喜んでくれて、吐き気が治まるような効果まであるのかと思ったら、嬉しくて。それから患者さんから頼まれれば弾くようになりました。そんなおり、清水玲子さんというプロのヴァイオリニストが子宮頸癌で入院してきたんですよ。彼女は入院中に病院でバイオリンが弾けないことに苦痛を感じていたので、一緒にコンサートをしませんかって誘ったんです。生まれて初めてバイオリンと共演することを覚えました。いろんな曲を練習して、モーツァルト、ベートーヴェンのソナタ、タイスの瞑想曲とかエルガーの愛の挨拶とかね。そしたら、どんどん患者さんがコンサートに来てくれるようになって、大阪でも院内コンサートの様子がニュースで紹介されたんですよ。

入院患者さんに対して院内コンサートをしていると患者さんとの信頼関係が変わってきます。僕はがんの治療を専門にしていますが、手術の説明の際には厳しい事を患者さんに言わなければいけない時があります。たとえば卵巣癌の患者には、「がんを全部摘出するために人工肛門を造設するかもしれません。人工肛門が嫌な場合がんが取り切れず、すぐに再発して死ぬかもしれませんよ。」と話すことがあります。患者さんにとっては「がんで死にたくない。けどがんを取りきるために、麻酔から覚めたら人工肛門になっているかもしれない。」というように選択肢がない中で辛い決断をしていただくわけです。そんな説明されると、誰だって嫌ですよね。せやけど、あるとき患者さんから手紙いただきました。
「先生から手術の説明を聞いてたら、怖くてこのまま病院から逃げ出したいと思い泣きたくなりました。 しかし、その晩、先生がコンサートを開いてくれて、その音楽を聴いてるうちに、この先生に手術してもらうなら、その結果人工肛門になったとしても、受け入れられると思うようになりました」
とかね。そんな手紙をくれるんですよ。びっくりするでしょ?

驚きですね。すごいことだと思います。でも、先生のピアノが特別なのでは?癒やしの効果が強いのだと思います。
榎本:いやいや、そんなことないよ!そんなことない! 本当に下手くそやから(笑)。 僕の患者さんはほとんどが癌の患者さんだから辛い病気と闘っているんです。中には小学生前の小さなお子さんや受験を控えたお子さんがいるお母さんもいます。 そういった患者さんは『今、がんで入院している場合と違うのに…』と思いながら、痛みや吐き気などの苦痛に耐えて『主人や子供のために頑張ろう』とい強い気持ちと『本当に治るのか、再発しないでいけるのか』という不安な気持ちが交差しながら入院生活を送っています。けれども、患者さんは色々な症状については主治医に相談するけれども、心底の悩みまでは通常明かしません。特に大学病院に勤める医師はちょっと近づきがたい先生と思ってられる患者さんも多く、中々心の中を明かしてくれません。また、一昔前は医者は「僕にまかしとき!がんばりや!」で済んだし、家族に「本人には癌であることを言わないでほしい」と言われたら、本当の病名を本人に告げずに治療していたこともありました。が、今はちがう。治療の説明をするときに、インフォームドコンセントといって、治療に伴って起こる可能性がある合併症(起こって欲しくないこと)について、その可能性が低くてもすべて患者さんに話します。すると、それを聞いた患者さんは、「悪いことがおこったらどうしよう」と益々不安になる。不安な気持ちになった時に、先ほど怖い話をした医師が、患者さんのために一生懸命下手なピアノを弾いている姿を見ると「この先生、近づきがたい雰囲気やし、怖い話もするし、おっかなかったけど、私たちがちょっとでも和んでくれたらと思って一生懸命演奏してくれてるんや」ということがダイレクトに患者さんに通じるんです。すると、医者と患者の距離がぐっと縮まって、信頼関係も深まるし、患者さんが持つ心の中の悩みもさらけ出して話してくれるようになるんですよ。

患者さんを思う気持ちがピアノになった!
榎本:新潟大学に赴任してきて、新潟でも病院で患者さんに対するコンサートをやりたいなと思って、大阪大学病院での院内コンサートのことを前病院長の内山聖先生に相談したんですよ。そしたら「それはいい話ですね」ってピアノ買ってくれることになったんです。でも予算が50万しかない(笑)。そこで、内山先生が全学の同窓会長やってる考古堂の社長さんに働きかけてくれて、社長さんは、「患者さんの癒しの為だったら」とピアノを寄付してくださることになって、ぽんっと大金出してくださったんです。すごいでしょ? 次は、楽器屋さんが、「患者さんのためだったらお安く提供しましょう」とかなり値引きしてくれたんです。ほんま、みなさんのご厚意で今の外来に置いてある立派なグランドピアノが買えたんですよ。新大病院では、病院行事としてのコンサートを、僕は年に2回、5月と8月に担当して、それ以外に、医療情報部の赤澤先生が年2回担当しています。また産婦人科に入院している患者さんを対象に不定期に小さなコンサートを開いています。病院のコンサートでは、前の神経内科の教授の西澤先生とも連弾したんですよ。シューベルトとかバッハとか。また阪大の時に共演していた清水玲子さんの娘さんもわざわざ大阪からきてくれて、ベートーヴェンやモーツアルトのヴァイオリンソナタを共演しています。医者の卵である医学部の学生さんにも参加して演奏してもらってます。ある学生は「演奏中にみせる患者さんの喜ぶ顔が本当に嬉しそう。患者さんの心の中に音がすっと入っていく瞬間を感じます」と話していました。8月のコンサートは、毎年大阪から僕の元患者さんが、何人かわざわざ新潟まで聴きにきてくれるんで、僕もうれしいですよ。

講義の時に医学生によくする話なんですが、最先端の医療機器を並べて重症の患者を治療する施設のICUは、日本語では集中治療室ですが、英語ではIntensive Cure UnitではなくIntensive Care Unitというんですね。即ち集中的にcure(治療)するところではなく、集中的にcare(気配り・配慮・心にかけること)をするところなんです。医師は病気そのものを治そうという気持ちが強いのですが、一番大事なのは病気をもつ患者さんに対する気配り・配慮なんです。患者さんに心をかけることなしに医療を行うと、時には患者さんにとって苦痛のみを与えることになります。医学生にはこれからも医療を行う上で大切な心を伝えていきたいと思います。

患者さんの思いに応える確かな匠の技がここにある!
最後にピアノ以外でもう一つ、榎本先生の魅力を教えてください。
榎本:魅力ではないんですが、僕が日本で初めて執刀した手術というのがあります。子宮頸がんの患者さんのピークが30歳台なんですよね。最近どんどん晩婚化が進み、初産年齢が30才を超えています。子宮がん検診は20歳からできるけども、若い女性はなかなか受診しないのが現状です。だから妊娠してから初めて産婦人科を受診し子宮頸がんが見つかるケースが多いんです。通常は妊娠中に1期以上の子宮頸がんが見つかったら、お母さんの命を救うために子宮がんの治療を優先し、赤ちゃんを諦めてもらいます。ですが、やはり女性は妊娠したら子供を産みたいじゃないですか。そこで、妊娠を継続しながら、がんも治すために、病変のある子宮頸部を摘出して、胎児のいる子宮体部を膣と繋ぐ手術をしているんです。これまで国内の成功例は10例でそのうち7例は僕が執刀しています。なにせ、普段は鶏の卵ぐらいの大きさの子宮が子供の頭ぐらいの大きさになっているので、一歩間違うと大出血になり大変難しい手術です。治療する以上、我々も責任をもってやっていかないといけません。もちろん、ガイドラインに書かれている標準的治療は子宮摘出であっても、どうしても子供を産みたいっていう方がおられるんですよ。不妊治療を何年もしてようやく授かった子だといわれたら、10年越しの恋が実って婚約し避妊を中止したとたんに妊娠した子だといわれたら、何とかしてあげたいと思うじゃないですか。その上で、自分の技量との対話、安全にできる手術なのか、赤ちゃんに障害が残ることはないのか、お母さんの再発のリスクは上がらないのか。充分に考えて、病院の倫理委員会にも客観的に評価してもらってやってるんですよね。ガイドラインに沿って医療を行うことはもちろん重要です。しかし、ガイドラインから外れる医療を患者が望んだ時、ただちにNOといわずに、最新の医学情報を参考にし、自分の技量と真摯に向き合い、倫理的にそういう治療をしてもいいのかを客観的に評価してもらって、どこまでなら患者さんの希望を叶えてあげるのか熟慮して答えを出すことが重要だと思っています。

(所属等は執筆時現在です。)
おすすめの記事
-
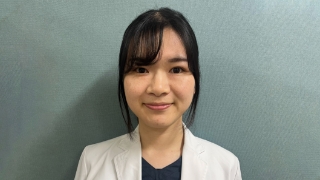
先輩医師インタビュー
医師・患者・研究者、3つの経験と視点を持つ腎臓内科医
山崎翔子 先生
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 腎研究センター 腎膠原病内科学
医師女性
- 分野 腎膠原病内科
-

先輩医師インタビュー
麻酔科医は縁の下の力持ち。術中の患者管理に力を発揮
小出燎平 先生
上越総合病院 専攻医
医師男性
- 分野 麻酔科
-
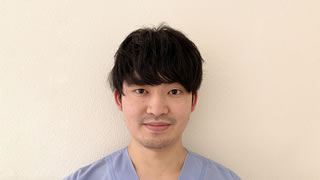
先輩医師インタビュー
生命に直結する疾患をカテーテルで治療するやりがい
古瀬博規先生
新潟県立中央病院 専攻医
医師男性
- 分野 循環器内科
-

先輩医師インタビュー
機能と外見でQOL向上に寄与し、人生を豊かに!
稲富 純一 先生
新潟県立中央病院 専攻医
医師男性
- 分野 形成外科
